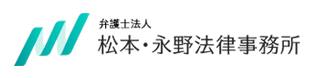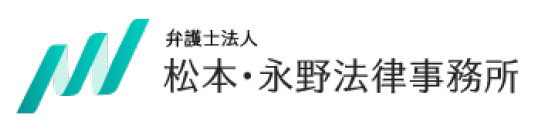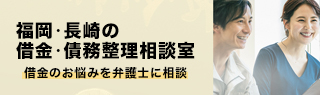事例002右大腿骨の変形障害(後遺障害等級第8級)を残した被害者につき、労働能力喪失率45パーセント、労働能力喪失期間を就労可能年齢(67歳)までとして、後遺障害逸失利益が算定された事例
- 担当弁護士永野 賢二
- 事務所久留米事務所
ご相談内容

依頼主
相続人:Bさん(40代・男性) / 職業:会社員
福岡県福岡市在住の40代会社員のBさん(男性)は、仕事を終え帰宅するに際し、原動機付自転車のライトを点灯させた状態で、交差点を青信号に従って直進していたところ、同交差点を右折した普通乗用自動車に衝突され、右大腿骨骨幹部骨折、腰部打撲、右膝打撲等の傷害を負いました。
Bさんは右大腿骨骨幹部骨折の治療のために、髄内釘骨接合術を受けリハビリを継続しましたが、その後骨癒合が遷延したために、横止めスクリュー抜釘(Dynamization)や横止めスクリューを挿入することとなり、骨癒合の促進及び改善のため、経皮的ドリリング(偽関節手術)を施行し、横止めスクリュー中枢・末梢共に抜釘の処置を受けましたが、右大腿骨の変形障害及び右下肢の短縮障害を残しました。
弁護士の活動

当事務所は、Bさんの後遺障害診断書等の医証を獲得し、後遺障害等級の申請を自賠責に行い、自賠責より、右大腿骨骨幹部骨折後の右大腿骨の変形障害(偽関節)として後遺障害等級第8級9号に、右下肢の短縮障害については一つの障害を複数の観点(複数の序列)で評価可能な場合には、いずれか上位の等級をもって、当該障害の等級とするとされていることから、上位等級である第8級9号として認定されました(なお、Mさんは、労災においても同じ等級を得ております。)。偽関節(仮関節)とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます(詳しくは、「上肢・下肢の変形障害」を参照してください。)。
そして、当事務所は、上記結果に基づき示談交渉を開始しましたが、加害者側は、「偽関節というだけの等級認定であるから、後遺障害等級第10級相当である」旨の主張を行い、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率を27%としたため交渉は決裂し、当事務所は適正な賠償を受けるため、福岡地方裁判所に訴訟提起しました。
解決結果

本件訴訟における主な争点は、①付添費、②後遺障害逸失利益でした。
付添費について、加害者側は、専門医の意見書を証拠として、「通院付添の必要性は否定されるべきである。」と主張しましたが、当事務所の立証活動により、裁判所は、当事務所の主張(入院・通院付添費全額)を採用しております。
後遺障害逸失利益について、加害者側は、医療記録を証拠として、「労働能力が21年間にも渡って45%も低下するものとは到底いえない。」「万が一、21年間の労働能力喪失が認められるとしても、逸失利益の計算を正確に行うためには、中間利息の起算点を事故日とする現価計算をしなければならない(事故時説)」と主張しましたが、当事務所の立証活動により、裁判所は、当事務所の主張(労働能力喪失率45%、労働能力喪失期間21年間)を採用しております。なお、事故時説とは、事故時と症状固定時が異なる場合には、事故時から労働能力喪失期間の終期までの中間利息の控除の係数から、事故時から症状固定時までのそれを差し引いたものを用いる(加害者側に有利な計算方法)ということですが、中間利息控除の基準時については、同説のほか、症状固定時説(被害者側に有利な計算方法)があり、この点に関する最高裁判所の判決の考え方は明確ではありませんが、実務の趨勢は症状固定時説で固まっています。
以上より、加害者側が、Bさんに対し、既払金(労災保険給付の損益相殺を含む)のほか4000万円を支払うとの内容で和解が成立し、結果として、大幅増額を実現することができました。
弁護士のコメント

付添費は、原則として、医師による指示がある場合、被害者の受傷が重篤な場合(判例上、上位等級を指す場合が多い)、被害者が高齢者、あるいは年少者(12歳以下)の場合、医学的観点から近親者の付添いの必要性が肯定される場合等に、被害者本人の損害として認められます。そのため、医師の指示はなく、高齢者や年少者でもない場合、付添の必要性及び相当性は明らかとはいえませんので、被害者の受傷内容及び治療経過を具体的に主張立証する必要があります。
また、変形障害については、認定基準がある程度具体的にあるために、その適用が争われるというより、その障害が残存したことによりどの程度労働能力に影響が生じるのかが争われる例が多いと思われます。しかし、被害者の治療経過等に加え、後遺障害の内容及び程度を具体的に主張立証し、労務にはもちろんのこと、日常生活にも支障を来していること等を明らかにする必要があります。
本件のように、示談交渉において、加害者側より、自賠責の等級より低い労働能力喪失率を提示されたとしても、訴訟により適正な認定を受けることは可能ですので、あきらめずに、弁護士に相談して頂きたいと思います。
文責:弁護士 永野 賢二