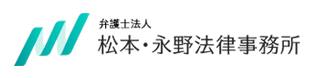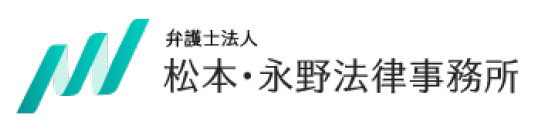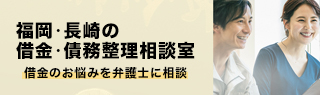1.脊椎障害定義
脊髄はいわば神経の束であり、脊椎はそれを保護する骨(脊柱を構成する個々の骨)です。すなわち、脊髄は、脳の最下部にある延髄の下に続いている棒状の神経細胞と神経線維の束で、脊椎により連なる脊柱の管(連結する椎骨の椎孔によって形成される管で、その中の脊髄を保護し、上は大後頭孔で頭蓋腔に続き、下は仙骨裂孔に開く)の中にあります。
脊髄損傷とは、脊髄を保護する役割を担っている脊椎が鈍的外力により損傷されることによって発生する疾患です。この鈍的外力が加わる原因としては、交通事故や高所からの転落、墜落が多く、それにより脊椎の骨折、脱臼などが生じるとともに、脊髄も損傷されることが多いとされています。
2.脊髄損傷による症状
(1)局所症状
損傷された脊髄の局所症状として、局所の疼痛、叩打痛、腫脹、変形、可動域制限などがみられます。そのほか顔面や頭部、腰背部などの体幹にしばしば挫傷、擦過傷、打撲などが認められます。
(2)麻痺
損傷された脊髄症状として種々の麻痺を呈します。
麻痺は、大きく完全麻痺と不全麻痺とに分けられます。完全麻痺では、損傷部以下の運動、知覚が脱失します。不全麻痺は、損傷の程度、高位によって様々な麻痺を呈します。障害部位ごとの麻痺の特徴は後述しますが、基本的に、頸髄損傷では四肢麻痺(両側の上・下肢すべてに生じた麻痺)、胸腰髄損傷では対麻痺(両下肢の麻痺)となります。
(3)全身症状
ア 循環障害
頸髄損傷及び胸髄損傷では交感神経が遮断され副交感神経優位になるため、心筋収縮力は低下し、心拍出量の低下、徐脈、血圧低下が起こり、血管運動神経の遮断による血管拡張はこれを助長します。
イ 呼吸障害
頸髄損傷では、特に呼吸障害に注意しなければならない。
損傷部位が高度になるほど呼吸障害の程度は重篤になる。横隔膜は第3~5頸髄節神経支配であるため、第3頸髄節以上の損傷では直ちに人工呼吸を行わないと救命できません。それ以下の頸髄損傷では、呼吸筋である肋間筋、腹筋群が麻痺するため、胸郭運動障害が起こり喚気不全となります。
ウ 膀胱直腸障害
中枢性あるいは末梢性麻痺により、排尿機能障害をきたした状態であり、尿閉、残尿、失禁、排尿遅延など、麻痺の程度で種々の症状がみられます。
副交感系の骨盤神経が膀胱利尿筋を支配し、尿意もこの神経を介して伝わります。一方、脳脊髄神経の陰部神経は外尿道括約筋を随意的にコントロールしています。両神経の中枢は第2、3、4仙髄にあり、大脳からの支配を受けています。
脊髄障害などで脊髄利尿中枢より上位で損傷された場合、反射が亢進し、少量の尿貯留で排尿反射が起こり、抑制は不可能となり、失禁となるが残尿は比較的少ない。一方、仙髄反射中枢や馬尾あるいは骨盤内での末梢神経の損傷すなわち排尿反射弓の損傷では排尿反射自体が消失し、膀胱内圧は低下し容量が増大し、残尿が多く、横溢性尿失禁となります。
脊髄損傷では膀胱直腸障害は必発であり、軽症例を除けば急性期はほぼ尿閉の状態であると考えられます。
3.脊髄障害の後遺障害認定
脊髄障害は、中枢神経系に分類される脊髄の障害です。したがって、脊髄損傷が生じた場合の後遺障害等級は、原則として、同じく中枢神経系に分類される脳の身体性機能障害と同様に、麻痺の範囲およびその程度ならびに食事・入浴・用便・更衣等の生命維持に必要な身のまわり処理の動作についての介護の要否および程度(常時介護・随時介護)により、別表第1第1級から別表第2第12級までの7段階に区分され認定されます。
麻痺の範囲に関する区分 麻痺の範囲
- 四肢麻痺 両側の四肢の麻痺
- 片麻痺 一側上下肢の麻痺
- 対麻痺 両上肢または両下肢の麻痺
- 単麻痺 上肢または下肢の一肢のみの麻痺
(麻痺の程度に関する区分)
区分 麻痺の程度 上肢における参考例 下肢における参考例
高度
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの。
- 完全強直またはこれに近い状態にあるもの。
- 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの。
- 三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの。
- 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動することができないもの。
- 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの。
中等度
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの。
- 障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または、障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの。
- 障害を残した一下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または、障害を残した両下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること。
軽度
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの。
- 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの。
- 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いものまたは障害を残した両下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしに階段を上ることができないもの
麻痺の程度は運動障害の程度をもって判断することとされ、麻痺の範囲およびその程度については、身体的所見およびMRI、CT等によって裏付けることのできることが必要とされます。
なお、労災保険においては、麻痺の程度を診療医が評価し、それに基づき後遺障害等級が認定されますが、自賠責保険では、診療医の評価に限定せず、被害者の生活実態を踏まえて後遺障害を評価する観点から、日常生活動作の制限程度を加味して身体機能障害の状態を把握し、改定労災基準に則って後遺障害等級が認定されています。
脊髄損傷に係わる自賠責保険の後遺障害等級は、以下のとおり労災認定基準の区分に応じてなされることになります。
自賠責保険後遺障害等級と労災認定基準における各等級認定区分
自賠責等級 労災認定基準における各等級認定区分
別表 級・号 脊髄症状の程度と就労可能の程度 介護の要否と程度★別表がありません
- 第11級1号 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常に他人の介護を要するもの
- 第12級1号 随時介護を要するもの
- 第23級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの(介護不要)
- 第25級2号 脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
- 第27級4号 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
- 第29級10号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
- 第212級13号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
そして、実際の当てはめにおいては、先に述べた脊髄損傷により残存した後遺障害の具体的内容である麻痺の範囲および麻痺の程度の組み合わせにより、以下のように整理されます。
脊髄損傷における麻痺の範囲および程度による障害等
等級 麻痺の範囲および程度
四肢麻痺 対麻痺 単麻痺
- 第1級 高度
- 中等度(要常時介護)
- 第2級 中等度(要随時介護)
- 軽度(要随時介護)
- 第3級 軽度(介護不要) 中等度(介護不要)
- 第5級 軽度 1下肢高度
- 第7級 1下肢中等度
- 第9級 1下肢軽度
- 第12級 軽微な麻痺等:運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺。運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの。
すなわち、ごく概括的には、四肢麻痺であれば3級以上、対麻痺であれば5級以上、単麻痺は5級から9級に当てはめられることとなります。
なお、自賠責保険の認定実務では、軽度の四肢麻痺(3級)もしくは軽度の対麻痺(5級)に至らない程度の障害については、ただちに12級とするのではなく、麻痺の程度および動作制限の程度に応じて、四肢麻痺では5、7、9級を、対麻痺では7級、9級を認定することができます。
また、具体的な脊髄損傷とそれによる後遺障害の内容と等級当てはめのイメージが理解しやすいように、以下のような参考例が示されています。
脊髄損傷における各等級の参考例
等級 参考例
- 第1級 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの
- 第2級 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖または硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの
- 第7級 第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖または硬性装具なしには階段を上ることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
- 第9級 第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
- 第12級 軽微な筋緊張の亢進が認められるもの。運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの
4.等級認定に参考とされる資料
脊髄症状の後遺障害等級認定にあたっては、症状固定時作成の後遺障害診断書は勿論のこと、脊髄症状特有の状態に関する医証が必須です。
麻痺による四肢の運動機能の低下、知覚機能の低下、異常反射、膀胱直腸障害、筋力低下、これらに基づく介護の要否、程度等を認定機関たる損保料率機構に正確に理解してもらうためには、「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」、「脊髄症状判定用」、「神経学的所見の推移について」などを用いる必要があります。脊椎の骨折や脊髄の被害を視覚的に証する資料として、MRI等の画像資料も非常に重要です。
その他、近親者や介護者等が記載する「日常生活状況報告表」によって、被害者の事故後の日常生活を具体的に理解してもらうことも必要です。
5.脊髄損傷をめぐる問題
脊髄損傷後の後遺障害の程度は多様であるとされる一方で、脊髄の解剖学上の構造、知覚・運動機能や反射等の緻密な神経学上の分析、さらには、画像診断の進歩による器質的病変の診断技術の向上などによる病態の解明が尽くされたかのような印象を持たれているといっても過言ではありません。その結果、これらの医学的情報で構築された診断においても根拠となる所見が抽出されないものや、得られた症状・所見と医学情報との整合性を欠くものが、裁判で争われることになります。
したがって、裁判上の争いとなるケースとしては、脊髄損傷自体の存否が争われるケースが多く、脊髄の障害があるとしたうえで障害の程度のみが問題となる例は少ないといえます。もちろん、既往の疾患がある場合には素因減額の争いが生ずることは珍しくありません。
(1)脊髄損傷自体の存否
ア 他覚所見の存在と整合性
脊髄の障害の後遺障害認定に係わる争いには、前提となる脊髄損傷自体の存否が争点となるものが多く、一般的に、脊髄損傷の発生を肯定するために検討されるのは、①画像所見上の裏付け、②神経学的な異常所見の存在、③症状の推移、④これらの整合性などということになります。
脊髄損傷の裏付け所見としては、脊柱(椎体)自体の損傷をあらわすもの(骨折等)がまず挙げられます。脊柱が骨折するぐらいであれば脊髄にも力が加わり、傷ついてもおかしくはないということになります。骨折等が発見できなくとも、椎間板ヘルニアや骨棘などによる脊髄の圧迫所見があれば、脊髄が傷害される可能性があります。
前述のように、脊髄を保護する脊椎に骨折・脱臼が生じている場合には、脊髄損傷の存在を裏付ける有力な他覚的所見となりますが、逆に、骨折・脱臼のない、いわゆる非骨傷性の脊髄損傷の場合には、脊髄損傷自体の存否が争いになることがあります。しかし、脊髄に何らかの異常所見が認められ、脊髄の障害によるものと思われる神経学的な異常が認められる例では、脊髄損傷等が肯定されることが多いといえます。
イ 既往の変性・障害の存在
明確な脊髄の損傷ないしは脊髄への圧迫所見などがなくとも、既往の変性などがある場合には、そのような脆弱性をもった脊髄周辺部に力が加わったために脊髄の障害が発生したのではないかという考えが生じてもおかしくありません。このような論理展開をする典型的な例としては、OPLL(後縦靱帯骨化症)や脊柱管狭窄等が存在する場合があります。もちろん、脊髄損傷の発生が否定される事案でも、このような既往の変性があるところに事故の衝撃が加わり神経症状が発生したとして(末梢神経系統の障害と評価することになろう)障害認定する例もあります。
脊髄損傷否定例画像所見もなく、神経学的な異常所見もなく、ただ感覚障害や疼痛だけを訴えている場合に、脊髄損傷の発生が認定されることはまずないといえます。しかし、異常所見的なものがあっても、脊髄損傷が否定されることはあります。
まず、画像上の異常といっても、脊髄に傷害を発生させるほどの異常とは評価できない場合(脊髄を圧迫するまでには至っていない等)が挙げられます。
次に、脊椎・脊髄の異常があるとされる位置と発生している神経学的異常の整合性がないとき(異常が発生しているように思われる脊髄の高位の髄節の支配領域ではない部分に神経学的な異常が現れている)などがあります。
また、麻痺などの症状が事故直後から発生しているのであれば疑問は起きにくいですが、事故後ある程度の期間が経ってから発生したとなると、脊髄損傷によるものとするには疑いが生じてきます。しかしながら、症状が遅発する合理的な理由付けができれば、脊髄損傷が発生したと認められることになります。
(2)中心性頸髄損傷の有無
下肢の症状があまりなく、上肢に障害が発生しているときには、中心性頸髄損傷との診断名が付され、その当否をめぐって争いになります。もちろん、画像所見、神経学的所見から脊髄の障害だと判断されれば問題はありませんが、そのような所見などが希薄な場合には、激しい論争となります。
このような争いの場合には、不完全損傷(不全損傷)、不完全麻痺(不全麻痺)の症状の多様性についてどの程度の医学的知見を提示し、かつ、脊髄損傷の存在とこれによる症状発生を裏付けるその他の状況事実が主張立証されたかにより認定がなされているといえます。
(3)その他
6.裁判実務
裁判例を検討すると、脊髄損傷の存否が争われた事案は、診断書上脊髄不全損傷とされているものや脊髄損傷と診断されていても実際には不全損傷であったりすることが多いと思われます。
そのため、脊髄損傷事案に臨む際には、脊髄損傷か不全損傷かといった傷病名だけでなく、脊髄損傷の原因や症状を詳細に確認することが重要です。
第1に、事故態様については、事故態様が軽微な場合に、脊髄損傷が生じるような外傷が加わったのかどうかが争いになることがありますが、脊髄がデリケートな部分であり、事故の状況によっては、わずかな衝突でも損傷することがありますので、どのような状況下で事故が生じ、どのような方向から衝撃が加わったのか、衝撃が加わる際被害者がどのような体勢だったのか、被害者以外の負傷者の有無及び負傷者がいる場合にはその怪我の程度といったことを詳細に検討することが重要といえます。
第2に、脊髄損傷から通常生じるとされる症状が被害者に生じていない場合には、脊髄損傷の内容を検討し、完全損傷か不全損傷か、どこをどのように損傷したのかを解明することが重要であるといえます。また、受傷後、麻痺等の症状の発生までの問にズレが生じた場合、脊髄損傷の症状と整合性が取れている部分の確認、頸椎捻挫等他の傷病で説明がつくのか、ズレが生じている部分及びその原因の検討を行うことが重要です。
第3に、既往症の存在については、特に高齢者の場合、まず診断書から既往症の有無を確認することが重要であるといえます。もっとも、既往症と相侯って脊髄損傷が生じたとして脊髄損傷が認められた場合であっても、公平の観点から素因減額として、損害額からの減額がなされることが多いことに注意が必要です。
第4に、完全な脊髄損傷では症状の説明がつかない場合には、不全損傷の可能性を検討する必要があります。裁判上も不全損傷であることを理由に脊髄損傷が認められることは珍しくはありません。しかし、当然のことながら不全損傷であればどのような症状でも認められるというわけではないことには注意が必要です。
まず、不全損傷であっても画像に出ることはありますから、画像検査が重要であることには変わりがありません。そして、その損傷態様及び傷病名によって麻痺の範囲・程度がある程度定まることから、麻痺の程度や範囲等について医学的に合理的な説明ができるのかを検討する必要があります。
いずれにせよ、不全損傷であっても、不全損傷の存否を明らかにする必要があり、不全損傷でも説明のつかないような麻痺の症状が生じた場合には、脊髄損傷の存在は医学的に説明がつかないとして、否定されることが多いといえます。
もっとも、結果的に脊髄損傷が否定されたとしても、事故によって脊髄損傷以外の傷害が生じ、その傷害によって後遺障害が生じている場合には、後遺障害と事故との因果関係は認められるから、常に多角的な視点で後遺障害の原因を検討する必要があります。
福岡・長崎で脊髄障害によるの後遺障害認定のご相談なら専門家の弁護士にお任せください
弁護士法人松本・永野法律事務所は福岡・長崎の脊髄障害による後遺障害認定について、これまで多数のご相談に対応してまいりました。
経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。