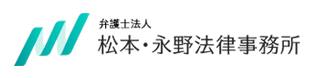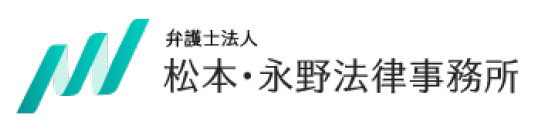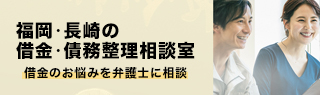事例008自賠責で因果関係なしとされた舟状骨骨折後の右手関節の機能障害を残した被害者につき、後遺障害等級第10級10号に該当するとされ、事故後に減収がなくとも休業損害及び後遺障害逸失利益が認められた事例
- 担当弁護士永野 賢二
- 事務所久留米事務所
ご相談内容

依頼主
Hさん(40代・男性)
福岡県広川町在住の40代事業所得者のHさん(男性)は、普通貨物自動車を運転し、信号機による交通整理の行われていない丁字路交差点を直進していたところ、同交差点を右折した普通貨物自動車に衝突され、右肩関節捻挫、右肘打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手舟状骨骨折等の傷害を負いました。
Hさんは、当初、右肩関節捻挫、右肘打撲、腰部打撲、頚椎・腰椎打撲捻挫と診断されましたが、事故から約2か月経過しても右手関節の症状が軽快しなかったため、MRI検査を受けた結果、右手舟状骨骨折が発覚しました。それから、Hさんは右舟状骨偽関節と診断され、右手関節の可動域及び疼痛改善のために遊離体(関節に引っかかっている骨片)の除去を行うこととし、関節鏡視下遊離体切除術が施行されました。
その後、Hさんはリハビリを継続しましたが、右手関節痛と右手関節の機能障害を残しました。
弁護士の活動

当初、加害者側は、Hさんの右手舟状骨骨折について、本件事故との相当因果関係はないとして、治療費の支払いを拒否しました(自賠責の事前認定手続においても同じ結論でした。)。
そのため、当事務所は、Hさんの右手舟状骨骨折と本件事故との因果関係や後遺障害診断書等の医証獲得のため、各医療機関に対しての照会や診療録等の精査を行い、意見書を作成した上で後遺障害等級の申請を自賠責に行いました。これにより、Hさんは、自賠責より、右手関節の機能障害(右手関節痛を含む)について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級第10級10号に認定されました(詳しくは、「上肢・下肢の機能障害」を参照してください。)。
そして、当事務所は、適正な賠償を受けるため、福岡地方裁判所久留米支部に訴訟提起しました。
解決結果

本件訴訟における主な争点は、①休業損害、②後遺障害逸失利益でした。
休業損害について、Hさんは、本件事故後、症状を押して業務を継続したことで、その収入は減収とならずむしろ増収となっていました。そのため、加害者側は、Hさんには休業損害の発生は認められないとの主張がなされました。他方、当事務所は、Hさんが業務の継続を余儀なくされた理由や、Hさんの特別の努力を具体的に立証し、増収の事実があってもなお、Hさんの潜在的な労働能力の喪失を観念することはできることを主張しました。これにより、裁判所は「結果的には減収になっていないが、労働能力喪失率も考慮し、3割の労働制限はあった」と認定しました。
また、後遺障害逸失利益について、加害者側は、「事業収入、事業所得ともに本件事故前よりも増加していることからすると、将来にわたっても、後遺障害による仕事への支障がなく、減収がない蓋然性が高い」として、Hさんの損害を否定しました。これに対し、当事務所は、裁判例を引用した上で、後遺障害の残存による現実の収入の減少や欠勤が認められない場合でも、Hさんの特段の努力や周囲の者の配慮によって事故前の収入が維持されているに過ぎず、あるいは事故前よりも多額の収入を得る機会を失ったものと考えられるから、後遺障害逸失利益の発生を認めるべきと主張しました。これにより、裁判所は「結果的には減収になっていないのは本人の特別の努力によるものと認め、逸失利益を認める」と判断しました。
以上より、加害者側が、Hさんに対し、既払金のほか1200万円を支払うとの内容で和解が成立し、結果として、大幅増額を実現することができました。
弁護士のコメント

本件では舟状骨骨折と事故との因果関係が問題となりました。舟状骨骨折の原因は外的要因により、手関節を背屈強制されて受傷することが多いとされ、性質上、①疼痛・腫脹が軽い、②転位の少ない骨折が多い、③舟状骨結節と重なり骨折線が見えにくい等(レントゲン診断は比較的難しく、単なる2方向撮影では見逃される可能性が高い。)により診断が遅れることも多く、捻挫と自己判断し、偽関節となってから受診することもあるとされています。そのため、本件のように因果関係が争いとなることが多いのですが、受傷態様や症状の経過等を具体的に立証することができれば、本件のように、事故から約2か月経過しての診断であっても、適正な認定を受けることができます。
また、損害について、事業所得者においては、原則として、現実の収入減少が発生していない場合には休業損害は認められませんが、被害者の努力や被害者家族の援助などによって減収が発生しなかった場合には休業損害が認められることもあります。本件事案では、Hさんに本件事故による現実の減収は生じていませんでした。しかし、通院等がなければ稼働時間外の私用時間であったものを、通院等のため稼働に充てた関係があるため、これをもって休業損害と評価する余地はありますし、本件事故による症状及び治療経過を考慮すると、治療期間中に一定の労働制限があったことは推認できますから、結果として現実の減収がなかったとしても、これをもって労働能力が回復していたとみるべきではないことは勿論、本人が職務に従事する際には、諸症状を我慢したりするなど相当の労苦があったことを考慮すべきといえます。そして、本件のように、加害者側より、減収がないとして休業損害や後遺障害逸失利益が否定されたとしても、具体的に主張立証することにより適正な賠償を受けることは可能です。
以上より、傷害内容と事故との因果関係を否定されたり、加害者側から損害を否定された場合であっても、あきらめずに、弁護士に相談して頂きたいと思います。
文責:弁護士 永野 賢二