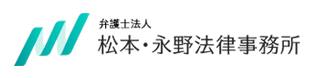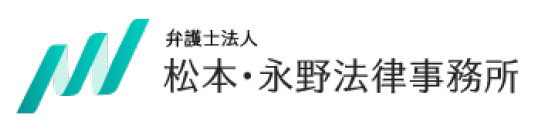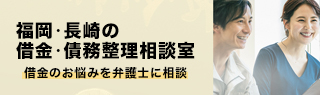1.給与所得者の休業損害とは
実際の減収分が損害になることが原則
交通事故の怪我のために入院や通院が必要となり、勤務先の会社を欠勤したため受け取る給与額が減ってしまった場合、事故に遭わずに働いていたならば得られたはずの収入との差額を休業損害として加害者に請求することができます。
なお、有給休暇を利用して給与を全額支給してもらった場合も、会社を欠勤していることに変わりはありませんので、休業損害を請求することができます。
減収がない場合について
そのため、 実際の減収がない場合には休業損害が認められないことが一般的ですが、例外的に減収がなくても休業損害が認められた事例もあります。
東京高判昭和50年9月23日(交民8巻5号1311頁)は、教師が通院に空き時間をあてたため給与等の減額がなかったものの、通院時間分を休業損害として考慮する扱いをしています。
また、大阪地判平成25年12月3日(交民46巻6号1543頁)では、本人や同僚の特段の努力によって減収を回避した場合には、一定の割合で休業損害の発生を認めるのが公平に資するとして休業損害を一部認めています。
他方で、治療期間中も痛みに耐えながら勤務を継続した旨の主張に対し、仮に、被害者が特別な努力をしたことが認められたとしても、減収が認められない以上、休業損害が発生したということはできない旨判示する裁判例もあります。
そのため、実務上は、傷害による不自由や苦痛に耐えながら就業を継続したとしても、減収がない場合には、休業損害を認めることには否定的な傾向が強いといってよいと思われます。
2.算定方法について
休業損害証明書について
給与所得者(いわゆるサラリーマン)の場合、「事故に遭わずに働いていたならば得られたはずの収入との差額」は、勤務先から休業損害証明書を発行してもらい立証することになります。
算定方法
算定方法としては、休業損害証明書記載の事故前3か月間の月例給与(毎月きまって支給される賃金残業代等の毎月変動する賃金はこれに含まれません。)支給額から、事故当時の1日当たりの支給額を算定します。なお、月額給与の変動が大きい職種等では事故前1年の給与総額を基礎とする場合もあります。
事故当時の1日当たりの支給額の算定は、一般的には、3か月間の月例給与支給額を90日で除した(割った)金額が用いられることが多いです。これに対して3か月間の稼働合計日数で除するべきだとの考え方もありますが、期間を通じて休業損害を認定する場合(土曜日や日曜日などの休業日についても休業損害を積算する場合)は、90日で除する考え方によることが合理的です。
(具体例)
30万円(月例給与)×3か月=90万円(事故前3か月間の月例給与支給額)
90万円÷90日=1万円(事故当時の1日当たりの支給額)
その後、事故当時の1日当たりの支給額と休業損害証明書記載の休業日数を、「休業損害額=事故前の1日当たりの収入額×休業日数」の算式に当てはめて休業損害額を算定することになります。
(具体例)
1万円(事故当時の1日当たりの支給額)×30日(休業日数)=30万円(休業損害額)
3.就労制限の程度による修正
ただし、実際に休業して勤務先から休業損害証明書を発行してもらっている場合であっても、当然にその全てが休業損害として認められるわけではありません。
仕事内容、受傷内容、治療経過、後遺障害の内容及び程度等を総合考慮して、実際の就労制限の程度を判断する必要があります。
すなわち、症状の改善に伴って労働能力の回復が認められれば、休業損害は、労働能力に応じて逓減(数量が次第に減る)的な割合で算定されます。
この点、普通乗用車同士の追突事故で頚椎捻挫等の傷害を負った被害者の休業損害について、「本件事故の態様、受傷内容、通院経過、被控訴人の業務内容等に照らすと、本件事故日から通院終了日である平成30年8月31日まで92日間のうち、本件事故後2週間については100%、その後上記通院終了日までの期間については平均して30%の休業につき、本件事故と相当因果関係のあるものと認めるのが相当である。」と判示している裁判例があります(東京地判令和2年10月29日)。この裁判例において、2週間を100%と認定している根拠は判例上明らかではありませんが、これは、医学上、捻挫の急性期(症状が急激に発現する時期)が受傷後~2週間程度とされているからと思料します。
特に休業期間が長期に及んでいる場合などは、上記修正がされる可能性があることに注意が必要です。
4.まとめ
このコラムでは、給与所得者(サラリーマン)の休業損害の考え方、損害の算定方法、就労制限の程度による修正についてご説明しました。
弁護士法人松本・永野法律事務所では、交通事故に豊富な実績を持つ弁護士が多数在籍しております。被害者の利益を最優先に考え、適正な損害賠償額を保険会社と交渉するなど、しっかりとサポートいたします。
交通事故に遭ったときはできるだけ早い段階で交通事故問題に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。